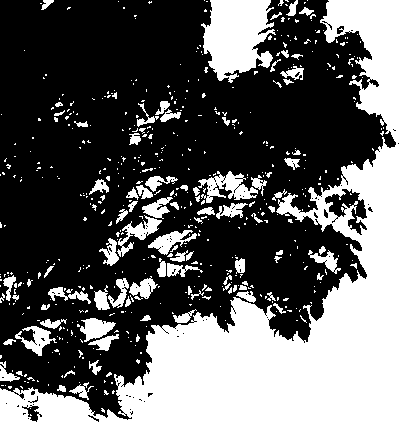
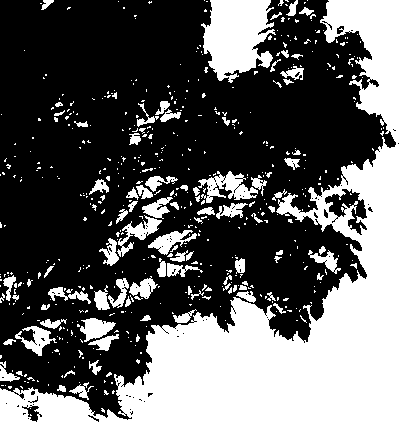
50,END.
| 目が眩むような白い空間は、あらゆる黴菌の侵入を許さない無菌室だった。 染み一つ無い白いベッドの上で、死人のように白い面の青年が、白雉の如くぼんやりと外を眺めている。嵌め殺しの大きな窓の奥には、突き抜けるような蒼穹が広がっている。 季節は、春だった。麗らかな日差しに、花々の優しい香りが漂うような気がする。 青年の瞳は、蒼穹と同じく透き通るように青かった。そして、短く揃えられた髪は銀色だった。 静寂に包まれた部屋に、ノックの音が転がった。 「ダイヤ、起きているか?」 無地の白い作務衣を纏い、銀髪の青年が起き上る。 さらりと流れた銀髪が、日光を反射して輝く。軋みながら扉が開いた。 「やあ、調子は如何だ?」 黒髪を揺らし、白衣を羽織った青年が現れる。穏やかな微笑みを浮かべる面と、脇に抱えたバインダーへ目を遣り、銀髪の青年はふっと溜息を零した。 「そんなの俺が知りたいね。なあ、如何なんだよ」 吐き捨てるように、侮蔑するように銀髪の青年が言う。面に浮かぶのは皮肉めいた嘲笑だった。 対面する青年は医師だった。胸元に張り付けられたネームプレートには、ジェイドという名前と共に彼の所属先、その素性が証明されている。 白い病室に溶けてしまいそうな銀髪の青年を見遣り、医師は慈愛に満ちた笑みを浮かべる。そして、バインダーを手元へ引き寄せ、青年と見比べた。 患者の名は、ダイヤモンド。十七歳、男性。 医師――ジェイドが研修医として当病院へ配属された頃から入院している。当時は一般的な個室にいたが、近年は無菌室を中心として其処から離れることは無い。 病名は無い。世界で初めての症例に、治療法は無く、現在の治療は対症療法の域を出ない。 ジェイドは、青年に言った。 「その様子なら、調子も良さそうだな」 青年は不満げに鼻を鳴らした。 ダイヤモンド――ダイヤの抱える症状は二つ。一つは先天性の免疫不全による感染防御機構の異常。つまり、外界からの刺激に弱く、紫外線により肌は焼き爛れ、小さな切り口からの出血は重篤な多量出血へ繋がる。年齢を重ねるに連れて症状は悪化し、日常生活も難しくなる。恐らく、ダイヤモンドは二十歳まで生きられないだろう。 そしてもう一つ。それこそが、ダイヤモンドがこの場所で生きる最大の理由だった。 青年は白い面を窓へ向け、動かない。横を向いた作務衣の背中が、歪に盛り上がっている。それはまるで、脱皮しようとする蝉のようだった。 後天性の奇形。ダイヤモンドの身体、主に背中の一部は少しずつ変異している。それだけではない。彼の細胞は外界からの刺激によって変異し、肉体的な異常を齎す。感染に対する抵抗力は弱いが、肉体的な強度は常人のそれを上回る。まるで、ダイヤモンドの変異は人間の進化を凝縮した図のようだと、ある学者は言った。 「なあ、ジェイド先生。退屈なんだ。このままじゃ病気よりも暇で死んじまうよ」 頭の後ろで腕を組み、背凭れに倒れ込むようにしてダイヤが言った。 十代の後半――。人間にとって重要な青春と呼ばれる時期を病院で過ごすダイヤへの同情は禁じ得ない。そんなダイヤへ朗報だと言うように、ジェイドは口を開いた。 「お客さんが来ているよ」 「誰?」 「ガーネット」 その名を告げた瞬間、ダイヤが弾かれるように身を起こした。 ベッドが軋むように鳴いたが、気にも留めずダイヤは蒼い瞳を爛々と輝かせている。 「ガーネット!」 ダイヤが子どものように、扉の向こうへ呼び掛ける。 曇り硝子に浮かぶ人影は、静かにドアノブを捻った。 「よう。元気にしていたか?」 紅い目をした精悍な男は、ダイヤを見ると気安げに手を上げて挨拶をした。 ガーネット。二十六歳、男性。ダイヤにとっては育ての親であり、唯一無二の親友でもある。 ダイヤの産みの親、つまり母親は出産と共に逝去した。父はダイヤとは異なる先天性の疾患によって世話をすることは出来ず、近付くことも出来ない。父――サファイヤは、先天的に帯電する体質を持っていた。彼が常に放つ微弱な電磁波は常人には影響が無いが、ダイヤにとっては生命の危険を伴う程に致命的な影響となる。名義と資金提供だけが、父親であるサファイヤの出来る最大の援助だった。 身体を起こすだけで、立ち上がることの出来ないダイヤは今にも宙に舞いそうに浮かれていた。犬ならば千切れんばかりに尻尾が振られていただろう。ガーネットは春先らしい淡い色彩の衣服を纏い、声を上げて来客を喜ぶダイヤをどうどうと往なしている。 「何だよ、ガーネット。来るならもっと早く言ってくれれば良かったのに!」 「驚かせようと思ったんだよ」 喜びを隠し切れず、否、隠そうともせずダイヤが口先だけでガーネットを責める。 傍に歩み寄ったガーネットは、慈しむようにダイヤの背を撫でる。歪に盛り上がった背中。肩甲骨が少しずつ隆起しているのだ。それはまるで、翼のように。 ガーネットはそれを不気味がるでも無く、まるで当たり前の器官の一つであるかのように受け入れている。病院関係者の中にもダイヤを畏怖する者は多く、学者は彼を研究対象と見做している。育ての親と言っても、まだ若いガーネットはダイヤと血の繋がりを持たない。彼の父、サファイヤからの膨大な報酬が目当てだと下世話な噂を流す輩もいるが、今のガーネットを見れば到底信じられる筈も無かった。 ガーネットはダイヤの傍の椅子を引き寄せ、どかりと座った。 「調子は良さそうだな」 「まあな。身体は元気だよ」 不貞腐れたように、ダイヤが答える。 病室は所謂無菌室だが、外界から齎される病原菌を排除する為に来客は着替えを行う必要が無かった。ダイヤの免疫不全、防御機構異常は、現在の医療科学では解明されない。ダイヤの身体は外界からの刺激を受けて確実に損壊されているのに、その要因が特定されていない。紫外線によって焼き爛れる肌も、春の日差しではまるで影響を受けないどころかプラスの作用すら働く。呼吸器を侵す空気も、創り出される空気の流れ――風さえあれば、呼吸は正常になる。外界から持ち運ばれた病原体も、ダイヤにとって好ましい環境さえ整っていれば死滅させられる。 それでも、ダイヤの生きる世界は常人とは異なる。分け隔てなければダイヤは生きられない。否、ダイヤを隔離しなければならなかった。 進化の縮図と呼ばれるダイヤの存在が、一般世間に知られれば、どんな影響が齎されるか。医療科学業界だけでなく、もしかすると人類へ直接的な影響が現れるかも知れない。 「外は良い天気なんだろう?」 「そうだな。日差しが暖かかった」 「いいなあ」 ぽつりと零された言葉に、一瞬、ガーネットが息を呑んだ。 羨望の言葉に隠された諦念。生まれてから殆ど全ての時間を病院で過ごしたダイヤに、外界を想像することは出来ないだろう。今更、外の世界へ出たところで浦島太郎のような存在で生きられる訳も無い。 この狭い病室以外に、ダイヤの居場所は無いのだ。 それでも、羨望を捨てないのは、ガーネットが来るたびに語る外界の話の為だった。彼が語る程に美しい世界ではないけれど、ダイヤの期待を裏切らぬ為にガーネットはきれいごとを告げ続ける。 「諦めてんじゃねーよ」 憎々しげにガーネットが言った。 「治せよ、しっかりと。それで、一緒に世界を見に行こうぜ」 「……ああ、そうだな」 治す。――ダイヤの症状に対して、治療という言葉が果たして正しいのかは医師であるジェイドにも解らない。 ダイヤが窓へ向かって手を伸ばす。歪に盛り上がった肩甲骨が、背中に影を落とした。 「羽根があればいいのにな。そうしたら、お前と一緒に何処へでも行けるのに――」 ジェイドは目を伏せた。ダイヤの命は恐らく短い。余命宣告をするのはきっと、ジェイドだ。 窓へ伸ばされたダイヤの手は――、そっと、取られた。 「行けるよ」 小さな掌が、ダイヤの手を包み込む。 春の日差しの中で、小さな影が浮かび上がる。眩んだように青い目を細めたダイヤは、息を呑んだ。喉の奥が奇妙に鳴る。呼吸器の異常では無い。心理的な作用だった。 病室に作り出された人工的な風が、ダイヤの髪を揺らす。青い瞳が驚愕に見開かれた。 「お前、」 ダイヤの声が震えた。 日差しに照らされ、黒い髪が輝く。大きな黒い瞳に、驚愕に染まったダイヤの顔が映る。 彼女の名前を知っている――。 呆然としていたガーネットが、思い出したように言った。 「そうだ。お客さんが、いたんだ」 ダイヤ手を取った女性が、微笑む。 「初めまして。学者をしているルビィを申します」 「学者」 訝しげに復唱したダイヤへ、ルビィもまた、応えるように頷く。 「そう。貴方を、此処から連れ出しに来たの」 「連れ出す? 俺はもう、何処にも行けないんだろう?」 学者なら解っている筈だと、ダイヤが嗤う。 けれど、ルビィは首を振って否定した。 「何処へでも行けるよ。貴方の身体は病に侵されている訳では無く、進化の途中なの」 「進化? これが?」 忌々しげにダイヤが言う。 「免疫不全、防御機構異常、後天性奇形……。常に新鮮な空気と風、適度な日光が無ければ呼吸すら儘ならない。これが、人間の進化か?」 「そう。貴方の身体は人類の中で最も早く、時代の変化に適応しようとしているの」 「適応、ね。屋内にも屋外にも、俺の居場所は無いんだ。完璧な管理の元でしか、生きられない」 「本当に?」 「何?」 「本当に、そう思う?」 何か確信を持って問い掛けるルビィに、ダイヤ思わず黙った。 自分がどんな気持ちで十七年を生き、どれ程の覚悟で外界を諦め、どういう思いで短い命を受け入れたのか、彼女に解る筈が無い。そう、思うけれど。 ルビィの横から、するりと前に進み出たガーネットが言った。 「色々話したんだけどな、お前の身体に、適した環境を探そうと思うんだ」 「どういうことだ?」 「だから、そのままだよ。狭い個室で、お前の身体に合わせた環境を作るのではなく、広い世界で、お前の身体に合う環境を探そうと思うんだ」 「無茶だ」 「だが、他に方法も無い」 そうだろう、とガーネットはジェイドに問い掛けた。 完璧な管理を行うこの無菌室でも、ダイヤが二十歳まで生きられる可能性は低い。 もしも、他に方法があるのなら、それはこの狭い個室にあるのではなく、広い世界にある筈だ。 ジェイドは己の医師としての矜持と葛藤しながらも、静かに頷いた。けれど、ダイヤは納得出来ないと喚くように訴える。 「外に出た瞬間に死んじまうよ。俺の身体は外界の些細な刺激に反応して、致命的な症状を引き起こす」 「一概にそうとも言えないだろう。お前の身体は現在の医療科学では解明されないところが大きいし、適度に自然と接することが生命維持に繋がっている」 諭すように、ガーネットが言った。 それでも信用出来ないと、否定の言葉を吐き出そうとするダイヤに、詰め寄るようにしてガーネットが言った。 「ごちゃごちゃ難しいこと考えてんじゃねーよ。此処で一生を終えたいのか? 外に出たくないのか? お前の望みは何だ?」 重ねられた問いに、ダイヤの瞳が灯火のように揺れる。 そっと顔は伏せられ、震える唇が確かに言った。 「世界を、見たい」 「――なら!」 ガーネットが、ダイヤの空いた手を取った。 「行くぞ!」 それは死地への旅立ちかも知れないし、可能性と言う名の希望かも知れない。医者として何が正しいのか、ジェイドには解らない。 縋るようにガーネットの手を握るダイヤは俯いたまま顔を上げない。白いシーツに、涙の跡が落ちる。 ルビィが言った。 「主治医として、可能であれば貴方も同行して頂きたかったのですが」 既に否定の形を取った言葉に、ジェイドは苦笑した。 「ああ。残念だが、俺は行けないよ。ダイヤの他にも多くの患者を抱えているし、それに――」 ジェイドの、翡翠のような瞳が、ルビィを見た。 「それはもう、俺の役目じゃないだろう?」 確認するように、ジェイドが言う。今度はルビィが苦笑した。 「そうですか。では、バトンタッチということで」 ルビィが微笑む。学者と言う彼女ならば、ダイヤを任せても安心出来る筈だ。 涙を拭ったダイヤが、目元を赤く染めて此方を見ている。十七年の月日を過ごしたこの病院――否、この鳥籠から飛び立とうとしている。 「ダイヤ。飛び疲れたら、何時でも帰って来いよ」 「ありがとう、ジェイド」 その時、騒がしく扉が再度開かれた。 現れた青年は蕩けるような蜜色の瞳で、縋るようにダイヤを見て言った。 「おい、ダイヤ! 今の話、本当か?」 「ああ」 転がり込んで来た青年――トパーズは、ダイヤと同じく当病院の長期入院患者だった。 長年闘病して来た戦友とも呼ぶべき存在が旅立とうとしているのだから、焦るのも当然だ。けれど、ダイヤの決意は揺るがないようで、自力で立ち上がることすら難しい、痩せ細った両足をベッドの傍に垂らした。 「無理するなよ。今、車椅子を」 「いや、歩く」 ジェイドの申し出を断り、ダイヤはガーネットに肩を借りながらゆっくりと立ち上がった。 彼が立ち上がるところを、随分と久しぶりに見たような気がする。痩せ細った足は体重を支えられず震えるが、ガーネットが力強くそれを支えていた。 一歩。ダイヤの足が踏み出される。骨が軋むような嫌な音がした。 また一歩。今度は揺らぐことの無い確かな一歩だった。 「辛い旅になるかも知れないぞ」 この後に及んで、トパーズが彼等の決意を鈍らせるようなことを言う。だが、ダイヤが笑顔すら浮かべて答えた。 「それでも、いいんだよ」 向けられた笑顔が、ジェイドに、既視感を覚えさせた。 それが何か等、もう誰にも解らない。 歩き出した彼等を止める者はいない。その後ろを追い掛けるルビィが、扉を出る前に小さく会釈した。 曇り硝子にダイヤの姿が浮かぶ。肩甲骨の奇形が、まるで、広げられた翼のように見えた。 無菌室を出ても、案の定、ダイヤの体調は崩れず歩行も安定していた。日々進歩する現代医療の粋を集めても、ダイヤの生命を維持することは出来なかった。完璧な環境を人工的に作り上げた結果がダイヤの今を保障しているけれど、この先のことは解らない。ダイヤの身体は、日々変化している。肩甲骨の奇形も、やがては皮膚を突き破るかも知れない。そうして変化し続けるダイヤの症状に、医療が追い付く保障は無いのだ。 今のダイヤを生かすものは医療かも知れない。けれど、未来のダイヤを生かすのはきっと、この世界だ。 ダイヤは、人類の進化の縮図なのだ。 そう論じた学者の説を、ルビィは殆ど確信にも似た思いで肯定している。そう考えると、これまで牢獄のような個室で生きて来たダイヤの十七年がとても尊いものに思えた。 「なあ、ルビィ、さん」 敬称を付けるべきか逡巡したらしいダイヤが、ガーネットに支えられながら振り返る。 白い面を春の日差しが照らし、青い瞳が宝石のように煌めいて見えた。ルビィは返事をする代わりに薄く微笑む。ダイヤが言った。 「前にも、あんたに逢ったことがあるか?」 ルビィ、二十四歳。性別、女。 自分よりも僅かに幼く、世間知らずだろう青年が小首を傾げる。ルビィははぐらかすように言った。 「下手糞な口説き文句ね」 「そんなんじゃねーよ」 気を悪くしたように、ダイヤが砕けた口調で言った。 「ただ、そんな気がしただけだ」 ダイヤとしては、ルビィの返答が肯定であっても否定であっても構わないのだろう。 凡そ同年代の青年に比べると純粋で幼いダイヤを、微笑ましく思う。ルビィは答える。 「もしかすると、逢ったことがあるのかも知れないね」 それが思い出すことも出来ない遠い過去なのか、想像も付かない遥かな未来なのかルビィにも解らない。 ダイヤが、ガーネットの支えを離れて自力の一歩を踏み出す。春の日差しから力を得ているかのように、その足取りは力強い。とても長い間寝たきりであった重症患者だとは思えなかった。 開け放たれた窓から吹き込んだ一陣の風が、銀髪を舞い起こす。 眩しい日差しの中で、ルビィは一瞬の幻を見た。 縒れた上衣を翻す銀髪の青年。煌めく水面のような青い瞳。広げられた白亜の翼。振り返る白い面には、確かに、微笑みが浮かんでいた。 「何してんだよ、置いて行くぞ」 何時か何処かで見た――見るかも知れない光景が、幻と呼ぶには強い現実味を持ってルビィの目に映る。 吹き抜けた風の奥で、笑っている青年の背には歪な肩甲骨がある。日に焼けていない白い顔を見遣り、ルビィは、笑った。 「今、行くよ」 もう、置いて行かないよ。 青年の幻が、そう言って笑ったような気がした。 |
2014.2.25