|
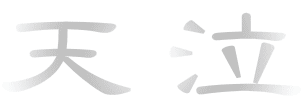
04.埋もれ木に花咲く②
吹き抜けた一陣の風に乗って、白い紙吹雪が舞った。そこで再び場面が切り替わる。
浮かび上がった鮮やかな夕日と、寂れた橋の欄干。寝床へと帰る烏の声がする。先程と同じ情景かと思えば、少し背の伸びた霖雨が一人とぼとぼと現れた。背負ったランドセルは更に草臥れている。其処には揶揄する二人の子どももいないけれど、霖雨の整った面は年に見合わぬ陰を帯びていた。それがこの飛ばされた数日か数年かの間に何があったかを物語っているようだ。
ふと、霖雨が足を止めた。目の前には欄干から川を眺める少年の姿。その手には何時かの霖雨を彷彿とさせるように一枚の画用紙があった。霖雨が黙ってその後ろを通り過ぎる。気付きもしない少年は溜息を一つ零すと、その画用紙を川にひらひらと舞い落した。
――あっ
声を上げたのは霖雨だった。驚いた少年が振り返ると同時に、欄干に足を掛けた霖雨がランドセルを投げ捨てて一気に川に飛び込む。何の躊躇も無く飛び込んだ先で飛沫が上がる。
驚いたのは少年ばかりではない。驟雨と林檎も言葉を失くした。
浮かんで来ない霖雨に嫌な予感ばかりがする。当惑する少年が欄干から覗き込む。すると、突然。音を立てて霖雨が、まるで曲芸をするイルカのように顔を出した。ずぶ濡れになりながらも、其の手には確かにあの画用紙が握られていた。
――見付けたよ
嬉しそうに笑う霖雨の顔を、初めて見たような気がした。けれど、驟雨は欄干から身を乗り出した少年に釘付けとなっていた。くっきりとした二重は生意気そうに吊り上っている。見覚えのあるその顔、間違える筈が無い。
「あれ……、あなた?」
そう、その少年は紛れも無く驟雨だ。
ずぶ濡れのまま土手を上がって来る霖雨を呆然と見る驟雨少年。霖雨は誇らしげに、其の手に持った画用紙を渡した。
――はい、どうぞ
純粋な、真直ぐな瞳だった。けれど、少年の驟雨が苛立ったように叫んだ。
――いらねぇよ、そんなもん!
ぶっきら棒に言い放った少年に、霖雨は酷く驚いた顔をした。感謝こそされても、怒鳴られるとは微塵も思わなかったのだろう。背を向けて歩き出そうとする少年に、霖雨がぽつりと言った。
――でも、すげえ上手だぜ
その言葉に足を止めた。その胸中を驟雨はもう覚えていない。少年が振り返るのも気付かず、霖雨はその絵画をじっと見詰めていた。
――これ、お前のお父さんだろ?
そう、其処に描かれているのは父の似顔絵だ。小学校の図工の課題で描いて来たもの。
じっと自分の描いた絵を見られるのが何だか恥ずかしくて、奪うように取り上げると霖雨が笑った。そこで漸く、驟雨は全てを思い出した。
幼少より、江戸時代から続く剣術道場の跡取りとして育った驟雨は、父の厳しい稽古を受けながら過ごしていた。幼い頃に亡くした母は顔すら覚えていない。あるとき、この絵画を家に持ち帰った。喜んでくれる、褒めてくれると期待して見せたその似顔絵を見て父は、そんなことをしている暇があるなら剣を振れと言って取り合ってもくれなかった。その悔しさから、せめてもの反抗心から毎日の稽古をほっぽらかしてこの場所にいたのだ。
霖雨がそんな背景を知る筈も無い。このときは、驟雨も霖雨の背景を知りもしなかった。だから、霖雨のことを馬鹿だと愚かだと罵ったのだ。でも、霖雨はその笑みを崩さなかった。
――大事にしろよ。亡くしてからじゃ、遅いんだから
そう言って両手を頭の後ろで組んだ霖雨の見せた、何処か寂しそうな微笑みを今でも覚えている。居た堪れなくなって目を伏せれば霖雨が笑う。
霖雨の言葉が引っ掛かって、両親の有無を問い掛けた。霖雨はその笑みを崩さずに言った。
――もう、いないんだ
何の陰も見せずに霖雨が笑うから、少年は目を伏せた。すると、霖雨がランドセルの中からくしゃくしゃの紙を取り出して見せた。
それはあのとき破かれた家族の肖像だった。随分と色褪せてしまっているけれどセロハンテープで丁寧に貼り合せた霖雨の胸中を思い、軋むように胸が痛んだ。
――俺が描いたんだ。お前みたいに上手くないけど
照れ臭そうに笑う霖雨に、少年は掛ける言葉を持たなかった。
そのときになって、そこに描かれているのが家族だけではないことに気付いた。僅かに残るピンク色は桜だろう。けれど、三人の後ろに描かれたクレヨンの茶色い線。
驟雨の視線に気付いた霖雨が、梅の木だと言った。
――梅は冷たい風の中でも咲いて、散っても香りを残す強い花なんだって。俺の好きな花なんだ
花が好きだなんて女々しいやつだなと笑おうとして、止めた。霖雨はまたその画用紙をランドセルの中に大切そうに仕舞い込む。じゃあね、と別れを告げようとした背中を呼び止める。
――お前、名前は
霖雨は、笑った。
――霖雨。常盤、霖雨だ
少年はその名を口の中で復唱し、離れていく霖雨に届くように大声で言った。
――何時か、この借りは返す! それで、もしもそのときお前が困っているなら、必ず助けてやるよ!
自分の口走った言葉に気恥ずかしくなって、少年は目を逸らす。友達でもないけど、と言った驟雨に、霖雨は微笑んで言った。
――友達になろうよ
明るく笑う霖雨が、音を立てて浮かび上がる水泡の向こうへと消えていく。大きな水泡が視界全てを覆い隠して、やがて再び闇が現れる。其処にはもう霖雨は勿論、少年の驟雨もいない。
静まり返った闇の中で、驟雨は思い出したように言った。
「あの後、霖雨はこの町からいなくなった。親戚の家に行くと言っていた」
既に色褪せた記憶は、もう驟雨には思い出せない。
林檎は静かに問い掛けた。
「あれが……あなたの言う約束?」
これまで何度となく驟雨の繰り返して来た約束という言葉が、このことに起因するのなら、なんて小さな誓いだろう。子どもの口約束を理由に、自分の危険も顧みないその行為は俄かには信じ難い。
けれど、驟雨は首を振った。
「さあな……」
それだけのような気もする。けれど、それだけじゃない気もする。驟雨自身にも解らない。
その時、闇の中に、それまでの静寂を打ち破るような荒々しい声が響いた。
――このクソガキ!
何かが壁に衝突する。怒りの形相で仁王立ちする男は、ランニングにトランクスという下着だけの見っとも無い恰好だ。ぼさぼさの頭と無精髭。よもやまともな大人には見えまい。罵声を浴びせる先に、腹を抱えて蹲る霖雨がいた。
あの夕焼けよりも少し背が伸びた。少年とも少女ともつかない端整な顔立ちが苦痛に歪む。衝突した箪笥の上から落下した小物が霖雨の上に降り注いだ。
男が、動けない霖雨の胸倉を掴んだ。
――お前みてぇなガキを、何の理由も無く引き取る訳ねぇだろ
霖雨の体は傷だらけだった。治り切らぬ生傷と、夥しい痣。振り上げられた男の拳が容赦なく霖雨を殴り付ける。体を丸めて痛みをやり過ごす霖雨から嗚咽が、喘ぎが聞こえる。
過去の記憶だということも忘れて駆け寄ろうとした林檎を、驟雨が止める。
――世の中にはな、お前みたいに顔の綺麗なガキがいいって金持ちもいるんだよ
舌舐めずりをする男の卑下た笑み。
――男も女も関係無い。俺がちょっと仕込んでやるからよ
――止めろ!
力で押さえ付けようとする男に、必死に抗う霖雨の細い腕が床に叩き付けられる。驟雨もまた、今にも飛び出していきそうな体を必死に押さえている。けれど、そのとき、霖雨の手が何かを掴んだ。それは、先程箪笥の上から落下した目覚まし時計だ。
振り上げた腕が、男を強かに殴り付ける。男の悲鳴が上がった。
血の滲む頭を抱え、呻く男を見下ろしながら、霖雨が肩で息をする。
――てめぇ……!
男の手が伸びる。竦んだまま動けなかった霖雨が、弾かれたように走り出す。ごみ溜めのような家を飛び出した霖雨が何処へ行くのかなど解らない。転がるように飛び出した霖雨の足取りがだんだんと遅くなる。見れば、靴を履いていなかった。
ぼろぼろの衣服、細い体。季節は夏だろうか。オレンジ色の外灯が照らす土手には青々と草木が茂っている。何かに導かれるように土手に座り込み、膝を抱える。微かに肩が震えていた。
噛み殺した嗚咽、震える双肩。誰も知らない。この少年が泣いていることなど、傷付いていることなど誰も知らないのだ。
やがて背を向けていた土手の上に一台の自転車が通り掛かる。警察官だった。未成年が出歩くには遅く、補導される時刻だ。声を掛けられた霖雨に表情は無い。名前や住所、年齢を聞かれながら霖雨は淡々と答える。人の良さそうな若い警官が、家まで送ると申し出る。霖雨の顔が引き攣ったことには、欠片も気付いていない。
一瞬、霖雨が口を開いた。けれど、すぐに閉ざされる。警官と共に家路を辿るその足取りは重い。
飛び出して来たあの家から、身なりを整えた男が顔を出す。
――どうもすみません。心配したんだぞ、霖雨
笑顔すら浮かべて、警官から霖雨を引き取る。微笑んで帰って行く警官が見えなくなった瞬間、男は開いていた扉を荒々しく閉じた。中に引っ張り込まれた霖雨が恐る恐る見上げた先に、背筋が凍るような怒りの形相の男がいた。
黒い羽根が風に乗って飛んで、霖雨の姿を覆い隠してしまう。次に何が映るのかは解らない。でも。
「――霖雨!」
何処にいるかも解らない人間に向かって、驟雨は声を上げた。
此処は霖雨の心の闇の中だ。それが何処まで深く、何処まで暗いのかは解らない。でも、こんな中に何時までもいたら此方までおかしくなってしまう。
「何処にいるんだ!」
過去は過去だ。霖雨の背負っているものが、どんなに重く苦しかったかは十分に解った。この先、更に霖雨を追い詰める過去があったとしても、過去の映像を眺めることしかできない自分達に一体何が出来るのだろう。霖雨を救う為に如何したらいいのだろう。
驟雨の声に、小さな光がふつりと浮かび上がる。それは導くように闇を漂い、小さな子どもの姿を照らした。
これも過去の映像だろうか、と驟雨は訝しげに目を細めたとき、その首筋に浮かぶ青痣が見えた。それは先程、体育館裏で金髪の男に殴られた傷跡だ。つまり、此処にいるのは。
「霖雨……」
膝を抱えて蹲るその姿は、先刻、土手にいた頃のままだ。周囲で声が響いている。
――あいつ、気味悪ィよ
――二重人格みてぇだよな
――何だか怖い……
――一緒に遊ぶの、止めよう
その声が何なのか解らない驟雨が辺りを見回す。過去の映像とは違って人影は何処にもない。けれど、林檎が言った。
「霖雨は昔から忘れっぽくて、酷い時には丸一日の記憶が無かったりするの。しかも、霖雨が忘れているその間はまるで別人みたいだって……。だから、周りの人は気味悪がって離れて行っちゃったんだって」
「それが、二重人格か」
驟雨は合点いったように頷いた。だが、言った。
「二重人格なんかじゃない。霖雨はただ、忘れた振りをしているだけだ」
「忘れた振り?」
「……この過去の映像、霖雨は全部覚えていただろう。それはさ、自分を守る為に闇の中に嫌な記憶を押し込めてきただけだ」
嫌なことを忘れようとするのは人間の心の防衛機能として普通のことだ。
そう思うけれど、驟雨は実際にその別人のようだという霖雨の姿を見た訳ではない。けれど、どんな理由があったって、霖雨が今此処でこうして独りで膝を抱えていなければならない理由にはならないと思いたい。
驟雨は膝を抱える霖雨の傍まで歩み寄る。その肩が微かに震えていることに気付いた。泣いているのだ。
「おい、霖雨」
霖雨は顔を上げない。
誰も、霖雨が泣いていたことなど知らないだろう。警官に向かって言おうとした言葉は、誰も知らないだろう。霖雨もきっと、この先口にする気も無いだろう。
それでいいと、霖雨は思うのだろう。それが正しいと、それが強さだと霖雨は思うのだろう。
「お前がずっと言いたくて言えなかった言葉、俺が当ててやろうか」
驟雨は少しだけ、笑った。
「助けて」
弾かれるように霖雨が顔を上げる。傷だらけの顔だった。驟雨は膝を着き、霖雨の顔を覗き込んだ。
「借りを返しに来たぜ」
「借り……?」
「解らないなら、それでもいい。でも、俺はお前を連れ戻しに来たんだよ」
すると、それまでの霖雨からは想像も付かないような皮肉めいた笑みを浮かべた。
「何処へ? 何処にも居場所なんか、無い」
霧状の闇が霖雨を包み込もうとする。けれど、驟雨は言った。
「あるだろう。世界中の誰がお前を馬鹿にしても否定しても、俺達はお前の味方だ」
包み込んでいく闇が静止する。虚ろな霖雨の目が、疑うように驟雨を見た。
「如何して?」
「はあ? オメーが言ったんだろ。俺達は」
蹲ったままの霖雨の腕を、林檎が、驟雨が取る。驚いたような顔でいる霖雨にも構わず、小さな光の元へと引っ張った。小さな光は少しずつ大きく広がっていく。
「お前の、友達だ」
光の中で、春馬が待っていた。擦れ違う刹那、微笑んだ春馬が掌を向けた。
「お帰り」
霖雨もまた掌を向ける。ぱちんと乾いた音がした。
途端に闇が弾けた。激しい明暗の差に目が眩んだ驟雨と林檎が倒れ込む。強かに打ち付けた頭部を撫でながら顔を上げると、其処は体育館裏ではなく、明るく清潔感に満ちた病院の一室だった。
規則正しく脈打つ電子音。白いカーテンが風を孕んで膨らむ。夜は明けたらしく、眩しい程の光が窓から差し込んでいた。
白いベッドに横たわる霖雨には不釣り合いな程に大きな呼吸器。閉ざされた瞼。
「……霖雨?」
ベッドの傍で、そっとその名を呼ぶ。すると、固く閉ざされていた目から一筋の滴が零れ落ちた。それを合図にしたようにゆっくりと大きな漆黒の瞳が現れる。
「俺にも、友達が出来たよ……」
誰に報告しているのだろう。驟雨は苦笑し、その頭を撫でた。
駆け寄った林檎が霖雨の名を呼ぶ。その眼には溢れんばかりに涙が溜まっている。
「霖雨!」
「林檎……、無事で良かった」
呼吸器を外して、起き上った霖雨。林檎がベッドに突っ伏して泣き出し、動揺しながらその頭を撫でる。霖雨にあの闇の中の記憶があるのかは解らない。けれど、どちらでも構わないと驟雨は苦笑する。
自分にとって、この男が何なのかは解らない。時の扉。春馬。解らないことだらけだ。けれど。
振り返った先で、霖雨の笑顔があった。涙を浮かべて怒鳴る林檎を宥めるその様は酷く穏やかだ。その様を見ると酷く安心するのだ。この場所を守る為に、此処にいるのだと心が告げる。
「霖雨、また学校で逢おうな」
それだけ言って去っていく驟雨を、霖雨は声を張り上げて呼び止めた。
「待てよ、驟雨!」
振り返らないまま、足を止めた驟雨に霖雨は言った。
「ありがとな」
驟雨は少しだけ笑って、扉を閉めた。二人だけになった病室で、林檎が訝しげに霖雨を見る。
「あの人、何者なの?」
「あいつは……」
何者かと聞かれて思い出すのは、あの時、金髪の男達が言っていた言葉だ。血の霧雨と呼ばれる男。剣術道場の跡取りだとか、一人で二十人近い人間を病院送りにしたとか物騒な情報ばかりだ。けれど、霖雨が出逢ったのはそんな男じゃない。
ぶっきら棒だけど、優しくて強い、一人の人間。そして。
「友達だよ」
そう言って微笑んだ霖雨が、とても晴れやかな顔をしていたから、林檎もまた追及するのを止めた。
窓の外には青空が広がっている。雲一つない空に、雨の気配は、無い。
|