|
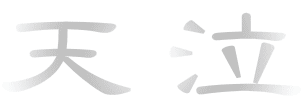
20.一陽来復
湿気と闇に包まれた体育館で、スポットライトの向けられた舞台だけが天国のように明るい。外で降り頻る激しい雨音が耳障りだと、壁に凭れ掛かりながら驟雨は思った。
張りぼての鬱蒼とした森の中を、幼い兄妹に扮した生徒が時折聞こえる鳥の鳴き声や木々のざわめきのBGMに怯え、辺りを頻りに見回しながら歩いて行く。此方まで浮足立ってしまいそうな、中々迫真の演技だ。樵の子どもという役割から質素でみすぼらしい出で立ちをしながらも、その整い過ぎた容姿は聊か目を惹き過ぎるとは思うけれど。
本日、体育館は演劇部の貸切だった。普段は高い競争率の中で運動部に割り振られているけれど、講演を間近に控える為に毎日二時間ずつ使用を許可されているらしい。部員数はぎりぎりながら、ボランティアやコンクールでの講演で高い評価を受ける春賀高校演劇部は何かと優遇されている。
スピーカーから拡張された声が体育館に響き渡る。聞き慣れた心地良い声は喧しい雨音を掻き消し、じわりと鼓膜を震わせてくれる。その声が微かに震えているのは、緊張しているからだろうか。
深い森の中を歩く二人の兄妹が探すものは幸せの象徴、青い鳥。闇色のローブを頭まですっぽりと被った魔法使いの老婆に、病気の娘を救う為に青い鳥を探すよう頼まれ、二人は犬や猫、光や水の精を仲間にしながら夢の中で思い出の場所や未来の国を訪ねるのだ。
しかし、結局、二人は青い鳥を見付けることは出来ない。
舞台上には疲労し、膝を着き絶望する二人の姿。スポットライトはだんだんと暗くなっていく。泣き出す幼い妹を慰める兄が気丈に振る舞う姿が、妙に目を引く。此方まで涙を零してしまいそうな演技に胸が軋むように痛んだ。
そして、二人は夢から目覚める。落ち込む中、気付くのだ。自分達の飼っている鳥が青いことに――。
「カーット!」
館内に響き渡る声と同時に、天井灯がぱっと灯される。
激しい明暗の差に目の奥がずきりと痛む。平気な顔をして動き回る部員達は大したものだと、見当違いのところで感心してしまう。
先刻の舞台に檄を飛ばすのは、顧問である麻田響子。担当科目は現代国語。27歳、独身。今時珍しい熱血教師ながら、一本筋の通ったその姿から、生徒からの信頼も厚い。
円になって麻田の指導を受け、腹の底から出した大声で返事をする部員達。中々良い姿だな、と他人事ながら思う。
そして、輪が弾ける。蜘蛛の子を散らしたようにそれぞれの役割をこなして片付けを始める傍ら、挨拶もそこそこに舞台を後にする一人の男子生徒。彼は部員ではない。助っ人として主役である兄、チルチルに抜擢された帰宅部員。
「――霖雨」
体育館を後にするその背中を呼び止める。しっとりと汗を掻いたYシャツが透けている。
ゆっくりと振り返る。足元から浮かび上がる金色の光の粒子を、驟雨は見逃さなかった。
(違う)
彼は、霖雨ではない。
振り返ったその整った顔立ちに並ぶ二つの眼球は、金色に輝いている。
「何か用か、驟雨」
春馬だ。
理解と共に落胆し、同時に安心する。自分の心の内が理解できず驟雨は苦笑した。
「霖雨は……?」
「疲れてるみたいだったから、代わった。霖雨に用があるなら、代わるが」
「いや、いい。休ませてやってくれ」
そうか、と無表情に春馬が言った。先日見かけたあの豪雨の中濡れ鼠だった春馬は何処にもいない。
掛ける言葉が見当たらないまま、その肩に触れようと伸ばした掌を握る。
授業の終了後、驟雨は霖雨を探していた。補習を受けるという霖雨には昼休みにも会うことが出来ず、そのまま放課後に突入してしまったが、クラスに向かうと其処でもまた会うことが出来なかった。演劇部へ助っ人に行ったと林檎に教えられたのはつい先程のことだ。
だが、結局、霖雨に会って如何しようというのだ。掛ける言葉など、ありはしない。謝罪や弁解が何になるのだ。
当たり前に自分を信じて友達でありたいと願った霖雨を、自分は勝手な庇護欲の為に裏切った。それは変えることの出来ない事実だ。
喧嘩なら数え切れない程した。人を傷付けることには慣れていた。離れていく人の背中を蹴り飛ばしたことも一度や二度ではない。だから、解らないのだ。如何すればいいのか解らない。謝らせたことはあっても、謝ったことはない。追い払ったことはあっても、引き留めたことはない。
どんな言葉を繋げば、霖雨への贖罪になるのだろう。何と告げれば、霖雨と友達になれるのだろう。
と、口を噤んだその時。無表情のまま、春馬が口を開いた。
「……霖雨は、何も怒っちゃいねぇよ」
自然と俯いていた顔を上げる。春馬は言った。
「裏切っただなんて、思ってもいねえ。あいつは絶対にお前を信じてる。お前が裏切っても、騙しても、何を言ってもな」
絶対の信頼。そんなものが向けられる日が来るなんて、考えたことも無かった。そして、そんなものが得られると思ったことも無かった。
「解るだろ? だからさ、霖雨は例えお前が裏切ったとしても、解りゃしねぇんだよ。お前を信じてるんだから」
「――何で」
すると、少しだけ寂しそうに、春馬が笑った。
「お前は霖雨にとって、初めての友達なんだよ」
解ってくれとも、解ってやれとも春馬は言わなかった。それが霖雨の意志を尊重している為なのだと解った。
不意に、霖雨の笑顔が脳裏を過った。無条件の信頼、無償の友情。そんなものを受け取る権利が果たして、自分にあるのだろうか。
守りたい。救いたい。起因不明の感情だけが先走って、霖雨の気持ちすら踏み倒してしまう。
「なあ、春馬、教えてくれよ……!」
如何したらいい、如何すればいい。訊くことは容易く、得られるものは少ない。だけど、それでも。
「俺は、俺自身が解らない……!」
知りたい、解ってやりたいから。
絞り出すように叫べば、数十秒の重い沈黙の後、静かにぽつりと春馬が零した。
「お前は――かったんだ」
体育館より響き始めた威勢のいい声に、春馬の声はかき消された。どうやら、運動部が体育館の使用を始めたらしい。
豪雨と体育会系特有の掛け声に届かなかった春馬の言葉は聞き取れなかったが、それが一般的に良いとされる内容でないことは、その苦々しそうな表情から十分に解った。それでも、知らずにはいられない。
春馬は噛み締めるように、今度は消えてしまわぬようはっきりと言った。
「お前は、霖雨を守れなかったんだ」
責める訳でも、嘆く訳でもなく。それはまるで、過去の悲劇を語るような口調だった。
「これは輪廻なのさ」
「輪廻?」
春馬が何を言おうとしているのか、解らない。けれど、その表情は決して冗談を言っている風ではない。
沈んだ暗い顔で、春馬は頷いた。
「過去に起こった悲劇が、魂の記憶として刻み込まれているんだろう。お前等にとっては、前世と言えば解り易いのか?」
死した魂は、また新たに生まれ変わる。前世の行いによって虫や畜生になる魂もあり、神になる魂もあるという。都市伝説の類として脳の片隅に留めていた記憶を、まさかこの男にこんなに大真面目な顔で問われる日が来るとは思いもしなかった。
そのまるでSFのような現象が本当に存在するのか、否か。学者でもない驟雨はそんなものに欠片も興味はない。
だが、もし、その非現実的な現象が実際に存在するとして、それが一体何だと言うのだ。その前世で、自分は霖雨を守れなかった。そんな馬鹿なと嗤ってやろうとして、失敗する。春馬は微塵も笑ってはいない。
「あの時、お前は霖雨を守りたかった、救おうとしていた。……凄惨さを極める地獄のような世界で、お前の存在だけを救いに生きようとしていた霖雨をな」
「……それで?」
否定の言葉は幾つも浮かんだが、話を止めるよりも先へと促す方が遥かに生産的だ。此方の思惑など看破しているだろう春馬は無表情のまま、一切の感情を読ませない。
「お前にとっても、霖雨は救いだった。その頃のお前等はまるで共依存のようだった。だが、霖雨はあることへの代償として自らの命を削り、お前は霖雨の為に命を差し出した」
「共倒れしたのか。それが、お前の言う過去の結末か」
バッドエンドもいいところだ。虚し過ぎて笑う気にもなれない。
春馬の話は、余りにも現実感が欠けている。薄っぺらだ。
「前世で救えなかったから、現世で救おうとしているってのか? 馬鹿馬鹿しい。俺は過去を引き摺る程、女々しくは無いつもりだぜ?」
「信じる信じないはお前の勝手だ。俺は、訊かれたから答えたまでだ」
気を悪くしたように、春馬は半身になって先を急ごうとする。
そのまま去ってしまわぬように、問いという名の楔を投げかけた。
「――なら、お前は?」
楔は、確かに突き刺さったようだった。踵を返そうとした春馬は、ぴたりと動きを止めている。
もしも、自分と霖雨が前世で出逢い、悲劇の結末を迎えたとして。それが理由で自分が必死に霖雨を救おうとしているというのも納得は出来ないが、理解は出来る。だが、そうだとしても登場人物が明らかに足りない。
時の扉より現れた春馬は、一体何者なのだろう。何時でも力を貸してくれて、助けようとしてくれる春馬は。
ゆっくりと振り返る春馬はまるで、油の切れた人形のようだ。
「俺は……」
微かに口を開き、閉ざす。何かを躊躇うような仕草に違和感を覚える。
ここのところ、春馬は何処かおかしい。完璧が服を着て歩いているような男だと思っていた。けれど、それならば絶対に見せる筈のない弱さを、自分は知っている。
「お前は、何者なんだ。俺にとっての霖雨が救いだったなら、お前にとって霖雨は」
「俺にとって……?」
すると、春馬はゆっくりと自らを抱き締めた。――否。霖雨を、抱き締めた。
「この子は、俺のたった一つの希望だ」
いとおしむように、守るように春馬は霖雨の体を抱き締める。言葉など無くても、春馬にとって霖雨がどれ程大切なのか、痛い程解った。
「どうして……」
驟雨がそう言った瞬間、弾かれたように春馬が顔を上げた。
驚愕に目を丸くした春馬は、凍り付いたように動かない。その異変に、春馬が見詰める先に目を動かした。
豪雨を背景に、一人の男が立っている。体育館へと続く渡り廊下の入口で、此方へ向くその面は人好きのする笑みを浮かべている。
「あいつは――」
名前を聞いた筈だ。見覚えがある。
あの男は確か。
「あんた、カウンセラーの……」
三間坂沈黙。そうそういないだろうその奇妙な名を、忘れる筈がない。
乾いた足音を響かせながら、ゆっくりと歩を進める三間坂が、何かを言おうと口を開く。だが、それを遮って春馬の声がした。
「三間坂ァ……!」
不倶戴天の敵だとでも言うように、三間坂を睨む春馬の目は憎悪に濁っている。こんな春馬は初めて見た。
今にも飛び掛りそうに身構える春馬はまるで毛を逆立てる猫のようだ。金色の光を宿す春馬の双眸は猛禽類のように煌々と輝いている。
「どの面下げて、此処にいやがるんだ……!」
「おやおや、随分だね。僕が君に何をしたと言うんだい」
苦笑混じりに、肩を竦めて三間坂が言う。状況に取り残された驟雨だけが目を白黒させる。
春馬は臨戦態勢だ。
「何をした、だと?」
髪が逆立つような怒りを浮かべ、春馬が低く言い放つ。だが、次を告げるよりも早く、三間坂が言葉を繋いだ。
「――朱鷺若領主、常盤春馬」
三間坂の言葉に、春馬の顔に一瞬奇妙な色が浮かんだ。
憤怒でも憎悪でもないそれは、驚愕だ。
「調べたよ、君のこと。常盤霖雨君は二重人格と聞いていたが、どうやらそれだけでは無いようだ」
くつくつと喉を鳴らしながら、三間坂は距離を詰める。驚愕からか身動き一つ出来ない春馬は蛇に睨まれた蛙のようだ。
「テレビ中継、見たよ。あれはただの高校生には不可能な芸当だろう」
「……それで」
「君達が、霖雨君の別人格を春馬と呼んでいるものだから、調べてみたんだ。霖雨君の生い立ちから、全てね」
「黙れ!」
春馬は声を上げた。
「気安く、霖雨の名を呼ぶんじゃねぇ!」
「なら、君の名を呼ぼうか。常盤春馬君」
三間坂は楽しくて仕方がないとでも言うように、からからと軽快に笑う。完全に遊ばれている。
状況を把握し切れないまま、驟雨が春馬を庇うように間に立った。
「あんた、教師だかカウンセラーだか知らねぇが、人のプライベート土足で踏み荒らしてんじゃねぇよ」
「桜丘驟雨君か。クク、中々おもしろくなって来たね」
何が可笑しい。
鼻で笑う三間坂を睨むが、さほど効果は無さそうだ。
三間坂が言った。
「全てを終決させる時が来たようだ。歯車は回り始めている」
「黙れ。これ以上、俺達に干渉するな! 時の扉は、お前なんかに扱える代物じゃねぇんだ!」
「そうだろうか。やってみなければ解らないだろう? 嘗ての君が。行ったように」
春馬は言葉を失った。この男は全てを知っている。それは驚愕ではなく、恐怖に程近い。
驟雨の目の前まで迫っていた三間坂が、その肩越しに手を伸ばそうとする。咄嗟に反応できなかったのは驟雨だけではない。春馬が無意識に張った予防線をいとも容易く飛び越えようとする三間坂。だが、その瞬間。
「――霖雨!」
弾かれたように霖雨は顔を上げた。その双眸は漆黒となり、視線は声の主を見遣る。
「大佐和」
クラスメイト、学級員、演劇部部員。
様々な役職を持つ同い年の少年が、此方の状況など何一つ知らないだろう笑顔を浮かべながら霖雨の手を取った。霧散していく金色の光は、驟雨と三間坂にしか見えないらしい。
「今日はありがとな。また明日も、頼むぜ」
無邪気な笑顔は、年齢以上に幼さを感じさせる。
状況を理解できない霖雨が曖昧に返事をすると、大佐和は思い出したように三間坂を見た。
「三間坂先生。麻田先生が、お呼びでしたよ」
「……そうか。何の用だろう」
「僕には解りませんので、直接伺っていただけますか?」
空中を浮遊する手は届くことなく、三間坂は苦笑し、霖雨の横を通り過ぎた。
体育館では演劇部が慌ただしく撤収の支度をしている。麻田も同じく、よく通る声で指示を飛ばしながら片付けを行なっていた。三間坂を探しているようには、見えない。
三間坂が尋ねると、麻田は首を傾げた。だが、思い出すように手の平を拳で叩き、笑う。大佐和とよく似た無邪気な笑顔だった。何か頼まれごとでもしたのだろう、三間坂が体育館に入っていく。麻田は、大佐和を見た。それはほんの一瞬。視線を交差させ二人は微笑んだのだ。
「何があったのかは知らねぇけど、困ったときはお互い様だぜ」
ぽん、と肩に手を乗せ大佐和が微笑む。きょとんとしていた霖雨も、釣られるようにして笑った。
助けられたのか。驟雨がそう理解した頃、大佐和は既に演劇部員の群れに戻り、片付けを始めていた。
残された沈黙が居た堪れなくて、霖雨は驟雨を見た。
「帰ろうぜ」
何事も無かったかのような素振りに、驟雨は頷くことしか出来ない。霖雨が何処まで知っているのか、何を解っているのかも判断不能だ。その笑顔の裏で実際に、何を思うのだろう。
歩き始めた霖雨をゆっくりとした歩調で追う。背中を向けたままの霖雨が言った。
「昨日は、ごめんな」
何の脈絡もない言葉は、豪雨にかき消されることなく驟雨に届いた。
霖雨が謝ることなど何一つない。そう言おうとして、驟雨は黙ってしまった。
「せっかく、看病してくれてたのに、追い返しちまってさ」
「そんなの、」
原因は俺にある。その言葉もやはり、発されることなく呑み込んだ。
自分の傲慢さに腹が立つ。謝罪の言葉一つ、碌に言うことができないなんて。お前が謝ることじゃない、と心の中で何度も呟いた。
だが、霖雨は背中を向けたまま、まるで何事も無かったかのように、当然のように言葉を紡いでいく。
「俺はさ、お前を絶対に信じてるよ。お前が何処の誰でも」
そうして振り返った霖雨は、何処か泣き出しそうに見えた。春馬の言葉が脳裏を過ぎる。
――裏切っただなんて、思ってもいねえ。あいつは絶対にお前を信じてる。お前が裏切っても、騙しても、何を言ってもな
霖雨はきっと、春馬の言葉など知らない。先程の遣り取りも知らないだろう。
きっと霖雨は、俺がどんなに馬鹿なことをしても許してくれるんだろうと思った。例え犯罪者として世界中に追われることになっても、霖雨だけは俺の無実を信じて探し出してくれるんだろう。それはきっと弱さではない。
信じると言った霖雨は、決して信じてくれとは言わない。見返りを求めない。
ならば、俺は与えよう。失う一方だったこいつが、これ以上傷付くことのないように。傷付いても、また顔を上げて歩き出せるように。
それでもいいよ、と許してくれるこいつを、守れるように強くなろう。
「ああ」
低く唸るような返事しか返せない自分を恨めしく思う。対等でありたいと、友達でありたいと願う霖雨に何を与えられるのかなんて解らないけれど。
今はそれでもいい。彼の進む先に光があるようにと、願いながら、共に歩くことが今の俺の出来る唯一のことだと思った。
豪雨はいつの間にか弱まり、雲の合間に光が見える。蒼天を眺める日も、遠くはない。
|